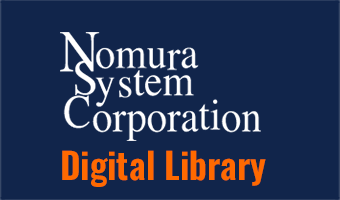DX
ベンダーロックインとは?起きる原因や回避策をわかりやすく解説
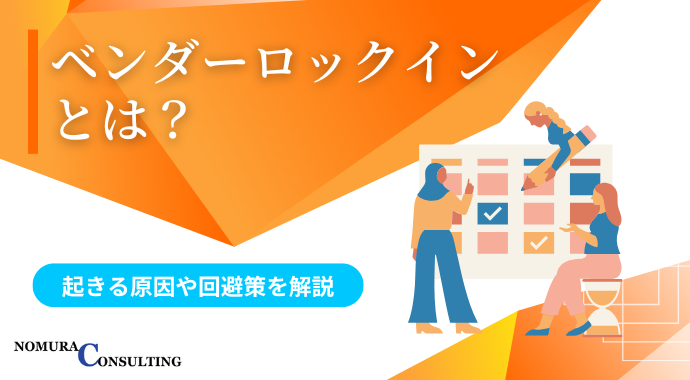
デジタル庁や公正取引委員会でも課題視されている「ベンダーロックイン」は、多くの企業や自治体が直面しているベンダー依存問題です。
本記事では、ベンダーロックインの現在の状況とデメリット、回避するための方法についてわかりやすく解説します。
ベンダーロックインとは|特定のベンダーに依存している状態
ベンダーロックインとは、システムの開発・運用を一部のベンダーに依存してしまい、別のベンダーに乗り換えるのが難しい状態のことです。
ベンダーロックインに陥ると、システム移行やリプレイスが困難となり、いわゆるレガシーシステム化につながります。
ベンダー依存状態では、システムを刷新しようとしても、その仕様を把握しているベンダーに頼らざるを得ず、高額な開発コストや保守費用を受け入れざるを得ません。
特定ベンダーに頼り、自社システムの保守・運用を任せることにはメリットもあります。
たとえば、ベンダーから一貫したサポートを受けられたり、長年築いた関係から親身に相談に乗ってもらえたりと、柔軟な対応を受けやすいのは大きな利点です。
しかし昨今では、DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進において、最新技術の導入を困難にするベンダーロックインが障壁となるケースがあります。
地方公共団体でも、下水処理場のDX化においてベンダーロックインへの対応が課題として指摘されました。
DX化を進めるためにも、ベンダーロックインを回避し、特定ベンダーへの依存度を下げることが重要です。
参考:AIによる下水処理場運転操作デジタルトランスフォーメーション(DX)検討会 – 国土交通省
ベンダーロックインが起きる原因
ベンダーロックインが起きる原因としては、以下が挙げられます。
- システムがベンダー独自の技術・仕様となっているため
- 仕様書などドキュメントが不十分、または最新化されていないため
- 契約や保守の制約により、別のベンダーへ切り替えづらくなるため
特定のベンダーの独自技術で構築されたシステムは、他ベンダーへの移行が非常に難しくなります。
また、仕様書などのドキュメントが不十分であったり、最新の状態に更新されていなかったりすると、移行のハードルはさらに高まるでしょう。
加えて、契約期間の縛りや違約金、特定のベンダーのみが提供できるサポート体制などが、乗り換えを難しくする要因となります。
ベンダーロックインのデメリット
ベンダーロックインによる主なデメリットは以下のとおりです。
- 古いシステムの利用継続を余儀なくされる
- ベンダーの影響力が強まり、価格交渉などが不利になる
- ランニングコストが高額になるおそれがある
特定のベンダーに依存し乗り換えが困難な状態になると、新技術の導入が難しくなり、業務効率の低下やセキュリティリスクの増大につながることがあります。
また、ベンダーがシステム管理・運用を独占することで、コスト面でも不利な契約条件を受け入れざるを得ない状況に陥ることも少なくありません。
以上のように、ベンダーロックインには業務効率化・セキュリティ・コスト面いずれにもデメリットがあるため、極力ベンダー依存から脱却することが求められます。
ベンダーロックインの回避策
ベンダーロックインから脱却するための方法には以下が挙げられます。
- 情報システムの疎結合化
- API等による情報システム間連携
- オープンソース化
情報システムの疎結合化
情報システムの疎結合化は、有効なベンダーロックイン対策とされています。
「疎結合」とは、システム間の依存度を最小限に抑え、個々のシステムが独立して機能できる状態のことです。
対して、システム間の相互依存度が高い「密」な状態になると、新規ベンダーは参入しづらく、ベンダーロックインの要因となります。
疎結合化により情報システムを細分化し、個別に調達することになれば、特定のベンダーやそのシステムに強く依存しない状態が実現可能です。
さらにシステム間の依存度を下げることで、新規ベンダーの参入が促進され、結果的にベンダーロックインからの脱却につながります。
API等による情報システム間連携
システム間でAPI連携が強化できると、特定のベンダーに限らず他ベンダーもそのAPIを利用してデータを扱えるようになるため、ベンダーへの依存が減らせます。
特定ベンダーに依存し、独自のフォーマットやデータ形式がシステム内で使われていた場合、新しいシステムとの互換性が確保しにくいです。
こうなるとシステム移行は困難となり、想定以上のコストや時間がかかる可能性があります。
API連携は、前項の「情報システムの疎結合化」を実施する上でも欠かせません。
APIを活用することで、独立した異なるシステム間でのデータのやり取りが標準化され、スムーズな連携が可能になります。
オープンソース化
情報システムのオープンソース化により、複雑な仕様のブラックボックス化を解消することは、ベンダーロックインの回避策となります。
システムのソースコードや設計書を公開しておけば、他ベンダーもシステム仕様の把握が可能となるためです。
オープンソース化の事例としては、東京都の「新型コロナウイルス感染症対策サイト」や国土地理院の「地理院地図」などがあります。
これらのサイトはソースコードが公開されており、Webサイト等でも自由に使用可能です。
官公庁の調査報告書によれば、「地理院地図」についてはオープンソース化により既存ベンダー以外もシステム把握が可能となり、複数ベンダー間で競争が発生したといいます。
ただし、オープンソース化には管理コストやセキュリティリスク増加の懸念もあり、すべてのシステムに適用すべきかは慎重に検討しなければなりません。
ベンダーロックインに対する公正取引委員会の調査報告
公正取引委員会では、ベンダーロックインに関して言及した「官公庁における情報システム調達に関する実態調査報告書」を公開しています。
同資料によると、情報システムの保守、改修、更改等の際に、既存ベンダーと再度契約することとなった理由の調査結果は以下のとおりです。
| 理由 | 割合 |
| 既存ベンダーしか既存システムの機能の詳細を把握することができなかったため | 48.3% |
| 既存システムの機能(技術)に係る権利が既存ベンダーに帰属していたため | 24.3% |
| 既存ベンダーしか既存システムに保存されているデータの内容を把握することができなかったため | 21.1% |
| 既存システムに保存されているデータに係る権利が既存ベンダーに帰属していたため | 7.1% |
引用:「官公庁における情報システム調達に関する実態調査報告書(2022年)」
上記の調査結果によると、半数にも及ぶ48.3%が既存システムの詳細を把握できておらず、既存ベンダーに頼らざるを得なくなっている状況です。
ベンダーロックインは独占禁止法に抵触する可能性もあり
ベンダーロックインによって他ベンダーの参入が妨げられることで、公正な競争が阻害され、独占禁止法に抵触するケースがあります。
独占禁止法とは「企業間の不公平な取引や市場の独占を防ぐための法律」です。
例えば、官公庁の調査報告書によると、ベンダーの「独占禁止法違反」となりうる行為には以下があります。
- 他ベンダーに委託しないよう要求し、自社のみとの取引を強要する(排他条件付取引)
- 虚偽の説明により、不必要な製品やサービスをまとめて購入させる(抱き合わせ販売)
上記をはじめとした独占禁止法違反行為は、競争の妨げとなるうえ、企業や自治体にとって不利な条件を生み出す要因として問題視されています。
ベンダーロックインに対する公正取引委員会の今後の対応
「官公庁における情報システム調達に関する実態調査報告書」では、ベンダーロックインに対する公正取引委員会の今後の対応について主に下記が言及されています。
- 設計・情報システムのオープンソース化
- 官公庁における組織・人員体制の整備
- 独禁法違反行為に対する対処
- デジタル庁との連携強化
DX化が推進されている現在において、情報システム同士が連携し合う状況でのベンダーロックインは回避されるべきです。
デジタル庁との連携も継続し、ベンダーロックインや独占禁止法違反行為の未然防止に取り組み、新規ベンダーが参入しやすい環境を整備していく方針と報告されています。
ベンダーロックイン脱却はDX推進のためにも重要
ベンダーロックインは、特定のベンダーに依存してしまい、システムの開発・改修・運用などにおいて他のベンダーへの切り替えが難しい状況に陥ってしまう状況を指します。
とくにDX推進を目指す場合、ベンダー依存により古いシステムの利用継続を余儀なくされることがあるベンダーロックインは障害となりえるため、未然防止や対策が必要となるでしょう。
ノムラシステムでは、知識やノウハウを持ったコンサルタントがDX推進をサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら