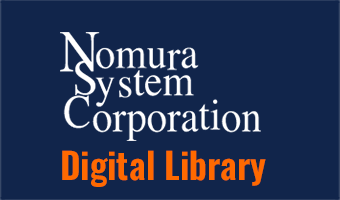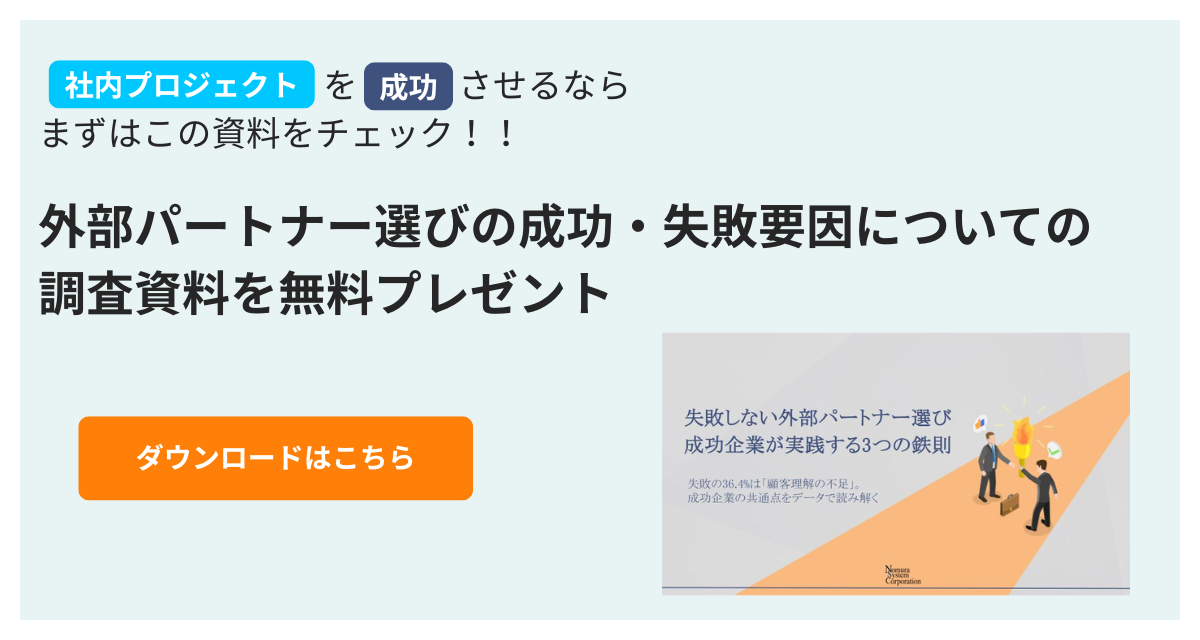RPA
RPAで行う業務効率化10選!できることやメリットを導入事例つきで解説
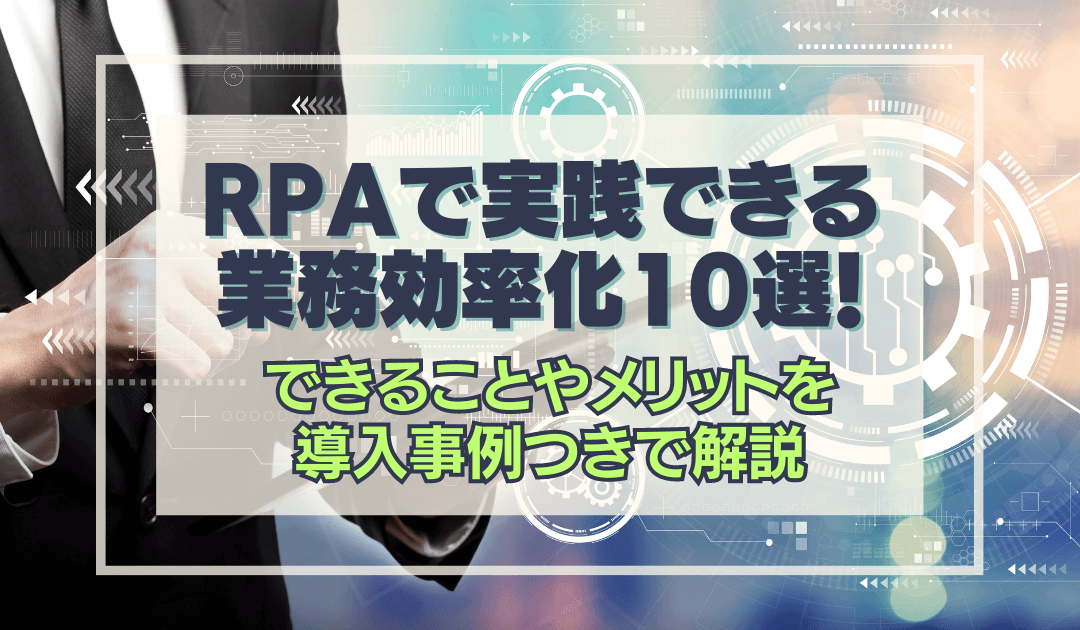
「2025年までに事務作業の1/3がRPAに置き換えられる」といわれており、現在RPAは大きな注目を集めています。
RPAは、人間の代わりとなり多くの業務を遂行できるため、人材不足解消や業務効率改善のためにと検討している企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、RPAの概要や効率化できる業務、メリットなどを導入事例つきで解説します。
参考:情報通信統計データベース|RPA(働き方改革:業務自動化による生産性向上)|総務省
RPAとは「ロボットによる業務効率化」のこと
RPA(Robotic Process Automation)とは、本来人間がPC上で行う作業をロボットを使用して自動的に業務を行うテクノロジーのことです。
ロボットといっても物理的に動くものではなく、PCやクラウド上でのみ動く仮想的なロボットです。
RPAを導入すると、以下のような効果を得られます。
- 複数のアプリケーションソフトをまたぐ業務プロセスの自動化
- 自動化させる作業内容の登録修正を現場担当者で実行可能
- 作業量の多い事務処理でも正確かつスピーディーに処理
- 24時間365日の稼働が可能
PC上で同じ作業を繰り返し行っている場合、RPAを導入すれば業務効率を一気に改善できるでしょう。
RPAで効率化できる業務10選
RPAが業務効率化できるものとして、以下のような業務があります。
- インターネット上の情報収集業務
- 入金消込業務
- 交通費確認業務
- 勤怠管理業務
- 見積書・請求書発行業務
- 受注登録業務
- 出荷業務
- 在庫管理業務
- 問い合わせ対応業務
- 売上日報作成業務
具体的にどのような作業が自動化できるのか例を挙げて紹介します。
営業・企画|インターネット上の情報収集業務
RPAを使えば、下記のようなインターネットを利用した情報収集も自動的に行なえます。
- 競合他社の価格情報の定期収集
- SNSでの口コミ収集
- Excelで集めた情報の集計
- 登録したキーワードを検知した際の担当者へのメール通知
人為的なミスが起こらないため、正確なデータをもとに自社製品と他社製品の違いを細かく分析できます。
経理|入金消込業務
入金消込業務とは、顧客との金銭取引を行う上でのデータ整理のことで、主に下記のような作業が挙げられます。
- 入金データと請求書データの照合
- 入金が確認できたものを消込
- 未入金リストの作成
- 入金額の相違や未入金は担当者へメール通知
これまで入金消込作業は、目視や手作業で行われていましたが、処理数や取引数が増加するほど、労力が必要です。
RPAで自動化できれば、担当者は、毎月数十件以上ある入金データの照合作業から解放され、コア業務に専念できます。
また、人間が作業していると入力ミスの可能性もありますが、RPAであればその心配はありません。
経理|交通費確認業務
提出された交通費精算書の金額が本当に合っているか確認するためには、多くの工数が必要です。
例えば、電車の定期券の値段を把握するためには、すべての従業員の区間の定期価格を調べなければならず、1つずつ間違いが無いよう確認していくのは多くの労力がかかります。
RPAを導入すれば下記のような工程を自動化することが可能になります。
- 精算書の交通費をWebで照合
- ルートや金額に問題があれば本人へ修正依頼メール通知
- 問題がなければ支払処理
実際の金額管理だけでなく、それぞれの従業員へのメール送信まで指示できるため、多くの作業を削減可能です。
経理|請求書発行業務
請求書発行で間違いがあれば、自社だけでなく取引先の手間を増やすことになるため、細心の注意を払わなければならない業務の1つです。
しかし、人間が行っていると、価格や品名などで記載ミスが起きる可能性があります。
RPAを導入すれば、下記の流れを組みミスを防ぐことができます。
- 営業担当者が売上伝票を共有フォルダへ保存
- 販売管理システムへ転記
- 登録した請求日に請求書を発行
完成した請求書を確認するだけで良いため、ヒューマンエラーの可能性をかなり低くできるでしょう。
総務|勤怠管理業務
勤怠管理は、毎月発生する上に従業員の人数に比例して工数が増加する業務です。
しかし、データ量に関わらず、勤務時間の集計や集計データに基づく給与計算などやるべき作業が固定されているため、RPAに適している業務といえます。
導入方法によっては、給与明細書の作成や振込まで自動化できます。
販売管理|受注登録業務
受注情報の中には個別対応が必要なものもあり、確認やソフトウェアへの入力などに多くの工数がかかります。
RPAで下記のようなワークフローを組んでおけば、多くの業務時間の削減が可能です。
- Webサイトから受注情報ダウンロード
- 個別対応の要不要で自動振り分け
- 個別対応不要の注文は受注管理システムへ登録
- 個別対応が必要な注文はフォルダへ保存し担当者へメール通知
工数の削減以外にも、判断する回数が少なくて良いため、1つの案件に関してきめ細やかな対応を行えます。
販売管理|出荷業務
最近では、デジタルデータでの受発注や出荷業務を行っている企業がほとんどですが、業種や取引先によっては、紙媒体での取引を行っている場合もあります。
しかし、AI(人工知能)やOCR(光学文字認識)などの技術を組み合わせることで、手書きの書類をテキスト化して、RPAのワークフローに組み込むことも可能です。
ただし、現在の技術では、個人差のある手書き文字を、完璧に読み込むことは難しいとされているため、読み込んだデータが正確かどうかは確認が必要です。
販売管理|在庫管理業務
在庫不足による販売機会の損失や過剰在庫による管理費の増大などは企業の業績に大きな影響を与えます。
しかし、RPAを導入することで、ECサイトや店舗などが複数ある場合も、変動する在庫数を自動的な更新が可能です。
設定数に達した時点で、通知を行うようにしておけば、いちいち在庫を確認せずとも安定的な商品の供給が可能になります。
顧客管理|問い合わせ対応業務
問い合わせへの対応スピードは、顧客の満足度へ直結します。
例えば、配送状況の問い合わせがあった場合、すぐに答えられなければ顧客の不満が貯まります。
RPAを導入すれば、顧客番号から追跡番号や配送状況の確認が瞬時に行えるため、すぐに回答可能です。
平均対応時間短縮につながることはもちろん、多くの顧客対応が可能になり、全体的な顧客満足度の向上につながります。
経営管理|売上日報作成業務
複数の店舗を運営する企業では、売上日報を作成し全店の収益を確認するケースがよく見られます。
しかし、売上日報は作成に時間がかかるため、従業員への負担が大きくなる上、店舗数が多くなるほど管理側も分析までの工数が増加します。
RPAで売上日報の作成を自動化すれば、従業員の労働時間削減や管理担当者の精神的負担を減少させ、企業全体の業務効率を向上させられるでしょう。
RPAで対応できない業務3選
RPAは工数削減に有効な一方、以下のような業務は対応できません。
- ルールのない非定型業務
- 人の判断を要する業務
- PC外の作業を含む業務
部分的な運用で効率化を進めることがおすすめです。
ルールのない非定型業務
RPAはあらかじめ登録されたルール通りに作業を繰り返すため、想定された状況以外では自分で判断できません。
以下のような業務では導入が難しいでしょう。
- ルール・作業手順が設定されていない業務
- 頻繁にルール変更が起こる業務
環境の変化を見越したルールの登録や想定どおりに進まなかった場合のカバー方法を決めておくなどの工夫が必要です。
人の判断を要する業務
RPAは想定外の環境下では力を発揮できないため、常に状況が変わらないようワークフローを組む必要があります。
例えば、ブラウザのバージョンアップによるボタンの位置変更やアプリケーションの仕様変更などが頻繁に行われる場合、抽出される結果やデータが大きく変わります。
想定通りの業務を行えるように、他社製品を使用する工程においては人間が行うようにしておくとよいでしょう。
学習機能を組み込むことはできないため、成長していくことはありませんがAIの発展によっては、これらの問題が解決されるかもしれません。
PC外の作業を含む業務
RPAはコンピュータ上でのみ動作するため、タッチパネルの操作や物品の移動など物理的な作業は行なえません。
加えて、RPAは手書き文字や手描き画像の認識が不得意です。
OCRでデジタルデータに変換して読み込ませても完璧な認識が難しいため、設定した業務工程に、アナログデータの使用は控えましょう。
特に、旧字体や形が似ている漢字などは、読み取り不良を起こしやすくなっています。
RPAで業務効率化するメリット
RPAの導入による大きなメリットは「売上向上や経費の削減」です。
圧倒的な速度で処理し、入力ミスが起こり得ないため、人間が関与せずとも業務を完遂できます。
担当者がデータ処理を行う負担が減り、業務負担が減った分、イレギュラーに対しても細やかに対応できるため、業務品質、売上の向上につながります。
また、RPAはロボットのため、24時間365日稼働可能です。
人のように退職や休職などで生産性の低下が起きず、日々の人件費・人材採用経費・研修費用なども必要ないため、経費削減効果もあります。
RPAによる業務効率化の導入事例3選
RPAは定型的な業務が多い業界で先行して導入されていましたが、現在では業種を問わず多くの企業や団体に導入されています。
ここではRPAで業務効率化した以下3つの導入事例を紹介します。
- 35040万時間の業務量削減|三井住友ファイナンシャルグループ
- 作業時間8時間から3.2時間へ短縮|アパマンショップ
- 登録業務の7割を自動化|東京ガス
350万時間の業務量削減|三井住友ファイナンシャルグループ
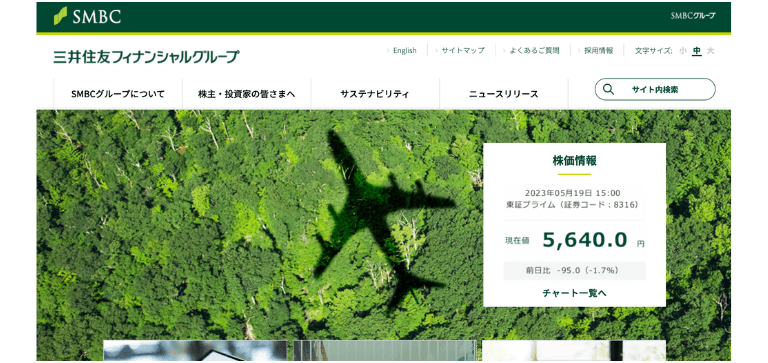
三井住友ファイナンシャルグループの1つ「三井住友銀行」では2017年からRPAを本格導入し、業務効率化を図りました。
結果、2019年度までに1,750人相当、350万時間という業務量を削減しており大きな効果を出しています。
2020年度から3年間の新中期経営計画では、三井住友銀行で150万時間、三井住友ファイナンシャルグループ全体で300万時間、1,500人相当の業務量削減を見込んでいます。
参考:業務改革を通じたコストコントロールと生産性向上|三井住友銀行
作業時間8時間から3.2時間へ短縮|APAMAN株式会社

引用:APAMAN株式会社
賃貸住宅を仲介する不動産会社「APAMAN株式会社」では、空室情報システムにおける入力業務の効率化を目的として、2018年から5店舗でRPAを試験導入しました。
結果、入力業務の作業時間は8時間から3.2時間へ短縮、40%もの業務効率化を達成できました。
この成果を受け、現在は直営店55店舗とFC加盟店に利用を拡大しています。
参考: RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を APAMAN グループが採用|APMAN株式会社
登録業務の7割を自動化|東京ガス株式会社

引用:東京ガス株式会社
都市ガスや電力を扱う「東京ガス株式会社」では、2017年から複数の業務にRPAを導入し、高圧電力新規申込の登録業務を70%自動化することに成功しました。
さらに、顧客へ送る明細報告書の作成業務にもRPAを導入したため、担当者のバックオフィス業務を年間270時間削減できるとしています。
結果を受け、他部署からもRPA導入の要望が出ているため、これから多くの部署で導入していくことが予定されています。
参考:WinActor®導入事例【東京ガス株式会社】「東京ガス」様×「WinActor」=「業務改革の源泉」|株式会社NTTデータ
RPAによる自動化で業務効率化・生産性向上を実現
RPAは、人材不足問題を解決するための有効打になり得る1つの手段のため、導入企業は徐々に増加していくでしょう。
また、現在の人員数で、より効率的に業務を進めて行く上でも必要です。
一度自社の業務を棚卸ししRPAを導入できる部分がないか確認しておくのがおすすめです。
弊社ではRPA導入による業務効率化をサポートいたします。
導入を検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。