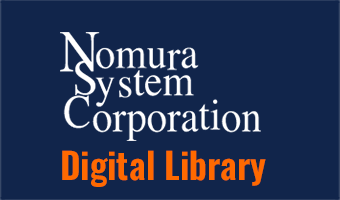DX
レガシーシステムとは?問題点や原因、脱却する方法をわかりやすく解説

レガシーシステムは、老朽化し最新技術への対応が難しくなったITシステムのことです。
長年の運用による複雑化や維持コストの増大が問題視されています。
本記事では、レガシーシステムの問題点や発生する原因、レガシー化を脱却するための方法をわかりやすく解説します。
レガシーシステムとは|老朽化したシステム
レガシーシステムとは、企業や組織で長年使用され続け、技術的に老朽化したITシステムのことです。
レガシーシステムは、業務に深く組み込まれている一方で、技術の進化に対応できず、保守・運用のコストが増大する問題を抱えています。
また、古いプログラミング言語やハードウェアに依存しているため、技術者の確保が難しくなり、システム改修のハードルが高くなることが多いです。
近年では、クラウド化や最新システムへの移行が推進されていますが、移行にはコストや時間がかかるため、多くの企業がレガシーシステムへの対応に苦慮しています。
経済産業省が発表した「DXレポート(2018年)」によると、企業がレガシーシステムを放置し続けると、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘されており、この問題は「2025年の崖」としても知られています。
関連記事:「2025年の崖」とは?問題点や対策をわかりやすく解説
レガシーシステムの問題点・デメリット
レガシーシステムによって起こる主な問題点として、以下が挙げられます。
- 保守・運用コストの増大
- 技術者不足
- セキュリティリスクの増加
保守・運用コストの増大
レガシーシステムの維持には、保守・運用コストが増大するという問題があります。
長年にわたる改修や機能追加により、システムが複雑化し、保守が困難になるためです。
たとえば、新しい機能を追加する際やトラブルが発生した際には、多くの時間と労力がかかり、結果として保守費用が膨らむことになります。
さらに、後述の技術者不足により、専門知識を持つエンジニアを確保するためにも高額な人件費が必要です。
こうした理由から、古い技術を維持するコストは年々増加し、レガシーシステムを抱える企業は負担を背負うことになります。
技術者不足
レガシーシステムに使用されている技術は、現在の主流から外れた古いプログラミング言語や開発環境が多く、対応できるエンジニアの確保が難しい状況です。
技術者不足を引き起こすレガシー言語の代表例としてCOBOL(コボル)が挙げられます。
COBOLは1959年に開発され、金融機関や行政機関、大企業の基幹システムで長年使用されてきました。
しかし、現在では新規開発に用いられることがほとんどなく、COBOLを扱えるエンジニア不足が進んでいます。
このように、古い技術に精通したエンジニアが減少し、技術者の育成や採用が難しくなると、レガシーシステムの維持はさらに困難となるでしょう。
セキュリティリスクの増加
レガシーシステムは、最新のセキュリティ対策に対応できないことが多く、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクが高まる重大な課題を抱えています。
たとえば、サポートが終了したレガシーOSなどを使い続けている場合、新たな脆弱性が発見されても修正プログラム(パッチ)が提供されないため、セキュリティリスクが高まります。
セキュリティリスクを低減するには、段階的に最新システムへ移行することが求められますが、移行が困難なレガシーシステムの性質上、対応を先送りにしてしまう企業も少なくありません。
レガシーシステムが発生する原因
レガシーシステムが発生する原因は、以下の5つが挙げられます。
- システムがブラックボックス化しているため
- 部署ごとにシステム導入されているため
- 開発ベンダーへ依存しているため
- 運用が属人化しているため
- 追加開発や改修によって複雑化しているため
システムがブラックボックス化しているため
レガシーシステムが生まれる原因のひとつは、システムのブラックボックス化です。
ブラックボックス化とは、システムの仕様や内部構造が十分に理解されておらず、限られた担当者しか把握していない状態を指します。
この状態になると、システムの維持管理や改修が困難になり、結果的にレガシーシステム化が進んでしまいます。
ブラックボックス化を防ぐためには、設計書や仕様書といったドキュメントを整備し、システムの見える化を進めることが重要です。
部署ごとにシステム導入されているため
企業や組織の各部署が、それぞれ独自のシステムを導入していることは、レガシーシステム化の大きな要因のひとつです。
これは「サイロ化」とも呼ばれ、部署ごとに異なるシステムが存在し、データや業務プロセスの統一が取れていない状態を指します。
各システムが異なる技術や仕様で構築されていると、統合や改修が困難になり、個別最適が進む一方で、全社的なシステムの老朽化が加速します。
その結果、システムの維持管理が複雑化し、必要なアップデートや統合が難しくなり、レガシーシステム化につながってしまうのです。
開発ベンダーへ依存しているため
レガシーシステム化の一因として、「開発ベンダーへの依存」が挙げられます。
長年にわたり特定の開発ベンダーに依頼し続けると、システムが独自仕様にカスタマイズされ、他社では対応できなくなるケースも少なくありません。
ベンダー依存によってシステムの刷新が難しくなり、老朽化したシステムを使い続けざるを得なくなると、結果としてレガシーシステムとして放置されるリスクが高まります。
このベンダー依存は「ベンダーロックイン」とも呼ばれる問題です。ベンダーロックインについて詳しくは以下の記事をご覧ください。
運用が属人化しているため
システムの運用が「属人化」していることも、レガシー化を加速させる要因です。
属人化とは、特定の担当者にシステム運用が依存し、その人以外が対応できない状況を指します。
属人化がレガシー化を招く原因は、運用や保守が特定の技術者に依存すると、システムの改修やトラブル対応が遅れ、結果としてシステムの維持が難しくなるためです。
さらに、技術者の離職や異動によりノウハウが引き継がれない場合、老朽化したシステムを維持することはさらに困難になります。
属人化を解消するためには、システム運用に関するノウハウや知識をドキュメント化し、複数の担当者で運用体制を構築することが必要です。
追加開発や改修によって肥大化・複雑化しているため
既存システムを追加開発や改修で対応している場合、レガシーシステム化しやすい傾向があります。
新しい機能や要求に対応しようと追加開発や改修が繰り返される結果、システム全体が複雑になるためです。
このようなシステムでは、古い技術やアーキテクチャに依存したまま新しい機能が追加されることが多く、技術的負債が積み重なり、時間経過とともに運用が困難となります。
システムが複雑化し柔軟性を失った状況では、最新技術の導入も難しくなり、最終的にレガシー化がさらに進行することになります。
レガシーシステムから脱却する手法
レガシーシステムから脱却する方法には「モダナイゼーション」と「マイグレーション」が挙げられます。
いずれも、システムの老朽化や複雑化を解消し、最新技術への刷新を目指すものですが、アプローチは異なります。
モダナイゼーション
「モダナイゼーション」とは、既存のシステムを完全に置き換えるのではなく、部分的に新しい技術を組み込み、システムの近代化を図る方法です。
モダナイゼーションでは、システムのコア部分をそのまま活用し、必要な部分を改善していくため、完全に新しいシステムを導入するよりもコストや時間を抑えられます。
例えば、オンプレミス環境からクラウド環境へ移行(リホスト)したり、ソフトウェアやハードウェアを刷新(リプレイス)したりするなど、システムを段階的に改善していく方法が一般的です。
マイグレーション
「マイグレーション」とは、レガシーシステムを完全に新しいシステムへ移行する手法です。
既存システムを引き継ぐモダナイゼーションとは違い、マイグレーションはレガシーシステムを一括して置き換えるという特徴があります。
システム全体を刷新し、最新技術に最適化することで、システムの効率化やセキュリティ向上に加え、拡張性や維持管理のしやすさも向上するのがマイグレーションのメリットです。
ただし、マイグレーションにはデータやアプリケーションの大規模な移行作業が伴うため、慎重な計画とリスク管理が求められます。
DX推進にはシステムのレガシー化を防ぐことが重要
レガシーシステムとは、技術的に古くなり維持管理が困難になったITシステムのことです。
レガシーシステムは運用コストの増大や技術者不足、セキュリティリスクを引き起こし、企業のDX推進を阻む要因となります。
レガシーシステムから脱却しDXを推進するためには、必要に応じて専門家の支援を活用しながら、段階的な移行を進めるとよいでしょう。
ノムラシステムでは、知識やノウハウを持ったコンサルタントがDX推進をサポートします。
DXについてお悩みの方は、以下よりお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら