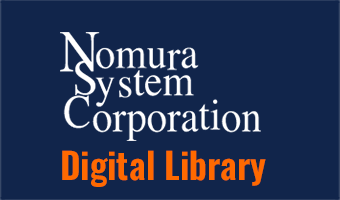コンサルタント記事
DX推進で陥りやすい課題とは?マインドセットが成功のカギ|DXの現場

- 飯田 悠紀
- PMO戦略部 兼 PMOコンサルティング事業部 シニアマネージャー
「DXの現場」では、ノムラシステムコーポレーションの現役コンサルタントが、SAPの導入をはじめ、DXに20年以上携わった経験から、DXで重要となるポイントについて紹介します。
今回のテーマは「DXで陥りやすい課題」です。多くの企業がDXの推進に苦戦している理由は「人」のマインドセットです。
本記事では「DXがなぜ難しいのか」という本質的な理解や、成功に必要なマインドセットについて、実践的な視点でお伝えします。
DXはなぜ難しいのか
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して既存の仕組みを抜本的に変革し、新たなビジネス価値を生み出す取り組みです。
私はDXを、産業革命のような大規模な変化だと捉えています。
例えば、かつては本を一冊ずつ手作業で複写していましたが、活版印刷の登場により、原稿があれば簡単に大量生産が可能となりました。
現在ではさらに進化し、デジタル技術を活用して紙の本だけではなく、タブレットなどのデジタルデバイス上でも書籍が読める時代になっています。
このような進化は、従来の活版印刷技術の改良だけでは、絶対に到達できませんでした。
デジタル技術の革新があったからこそ、紙の本だけなく電子書籍という媒体でも本が読めるようになったのです。
このようにDXとは、個別プロセスの最適化だけでなく、デジタル技術を取り入れることによる抜本的な変革が求められます。
従来の発想の延長線上では達成できない、ビジネスモデル全体の変革が求められるからこそ、DXは難しいのです。
DX成功を阻む「マインドセット」とは?
現在、社内にDXをもたらすツールは数多く存在します。
システム自体は設計通りに動きます。しかし、それを活用する側のマインドセット次第で、DXの成否が大きく分かれるのです。
マインドセットとは、新しい仕組みや変化に対する心構えや姿勢のことです。DXを成功に導くためには、推進する側と実務を担う側、双方に適切なマインドセットが求められます。
推進者に必要なマインドセット
DXの推進者に必要なマインドセットは「何がなんでも成し遂げる」という強い意思です。
前述した通り、DXとは社内における変革です。簡単な道のりではありません。
DXで解決したい課題に対して、何が必要で、どのような方法で実現するのか。その道筋を明確に描き、やり遂げる覚悟が求められます。
DXの現場において「専門的なことはわからないので、お任せします」という声を耳にすることがあります。しかし、システムの導入から運用まですべてを外部に委ねてしまうと、自社での活用方法が見えず、結果として導入目的を達成できないことにつながります。
プログラミングの詳細を理解する必要はありません。しかし、業務の流れとプロセスを把握し、「自分たちの手でDXを成功させる」という強い意志を持つことが、何よりも重要です。
その強い意志は、必ず組織全体に波及していきます。それは社内でのDXの機運を高めるだけでなく、実務を担う方々の意識を変えていくきっかけとなります。
実務を担う方のマインドセット
実務を担う方のマインドセットもDXには重要です。
DXにおいて、多くの現場で直面するのが「業務プロセスが変更となることへの不安」です。実務の担当者には長年慣れ親しんだプロセスがあるため、新しいシステムへ移行に不安があるのは当然です。
しかし実務担当者の不安に寄り添わずにDXを推進した場合、現場から
「これまでの方法が慣れていてやりやすい」
「業務が変わり、システムをどう活用すれば良いのかわからない」
といった声があがり、結果としてDXの効果が限定的になったり、導入したシステムが活用されずに従来の手法に戻ってしまうこともあります。
しかし近年、スマートフォンのアプリが自動でアップデートされ、新しい機能が追加されることは珍しいことではありません。
仕事とプライベートで領域は異なるかもしれませんが、私たちには変化を受け入れる素地があるはずです。
DX推進者は、実務担当者の不安に寄り添い、丁寧な対話を重ねることで、新しい変化を前向きに受け入れられる土壌を作ることが重要です。
このようなマインドセットの課題に加えて、DX推進をより複雑にしている要因があります。それは、同じ業態・業種であっても、各企業固有の特性によってDXの進め方が大きく異なるという点です。
業態・業種が同じでもDXの導入フローは大きく異なる
私たちはこれまで、数多くのDX推進プロジェクトに携わってきましたが、よくある誤解の一つが、同じ業態や業種であれば、DXの進め方は近似するのではないか?ということです。
実は、業態・業種が似ていても、DXの導入フローは大きく異なります。この点もDXが難しい点の一つだと考えています。
例えば鉄道会社の場合、主要な収益源が運賃収入だと考える方も多いかもしれません。
しかし実際には、一部の鉄道会社では、不動産開発や商業施設運営からの収益が運賃収入を上回っています。
このように、一見同じ「鉄道会社」でも、そのビジネスモデルや収益構造は大きく異なります。そのため、ある企業で成功したDXを、同業他社にそのまま適用することはできません。
各企業固有のビジネスモデルを深く理解し、その特性に合わせたアプローチを見出していく必要がある。だからこそ、DXは簡単には進まないのです。
また、このような企業固有の特性を理解し、適切なDXを推進するためには、全社的な視点が不可欠となります。
全社横断型でのDXプロジェクトを推奨する理由
DX推進のご相談は、人事部や経理部、営業部など、さまざまな部署よりいただきます。
結論から申しますと、特定の部署から全社DXを実現するのは困難です。
その理由は、各部署の視点や評価基準が大きく異なるためです。
例えばある企業において、経理部では全社的なコスト削減が重視され、一方、売上拡大を目指す営業部では、業務効率化のために積極的に新規システムに投資しようとしている場合があります。
この場合、DXを推進する部署によってDXの方向性が大きく異なります。
だからこそDXを推進するには、全社のビジネスモデルを深く理解した上で「どのような経営課題を解決するのか」を明確にすることが重要です。
この課題を解決するためにも、個別部署のKPIにとらわれない、専任のDXプロジェクトやDX推進室の設置をおすすめしています。
また、外部の専門家の視点も取り入れることで、社内の既成概念にとらわれない客観的な分析と効果的なDX推進も可能となります。
DXの推進において重要となるのが、DXツールの効果的な活用です。
多くの企業が陥りがちな誤解の一つが「DXは全て自社で開発しなければならない」という考えです。しかし、実際にはそうではありません。
自社でDXツールを開発する必要はない
自社の力だけで、DXを推進するのは困難です。
冒頭にお話しした電子書籍を例にすると、書籍をデジタルで販売することが目的だったにも関わらず、タブレットなどのデバイスまでゼロから開発しているのと同じです。
すでにあるデジタルデバイスを活用することによって、当初の目的であった電子書籍の出版が効率的に実現できるのです。
実際、DXツールとして活用されることの多い、SAPなどのERPやIT SaaSでは、多額の研究費用が投じられています。
例えば、2023年のSAPの研究開発費は約63億2400万ユーロ、同年のセールスフォース社の研究開発費は50.55億ドルです。
DXの実施に、日本円にして60億ユーロ(約1兆円)の資金を投じるのは、現実的ではありません。
すでに大規模な投資が行われている信頼性の高いサービスを活用することで、自社のDXを効果的に進めることが可能です。
例えばSAPでは、業務プロセスの標準化や効率化のサポート、企業全体のデータを統合し、必要であればほぼリアルタイムでの可視化ができます。一元管理も可能なため、迅速な意思決定にも役立ちます。
このように競合企業がDX推進を積極的に進めている中で、自社の取り組みが不十分であれば、競争力に差がついてしまう可能性もあります。
世界的な規模で投資され、信頼性の高いサービスを活用することは、時代の変化に対応し、ビジネスを持続的に成長させる上で重要な選択となります。
まとめ:DX推進はマインドセットから
DX推進の過程では、様々な課題に直面します。しかし、その多くは技術的な問題ではなく、「人」のマインドに起因していることが少なくありません。
推進者は、自社のビジネスモデルを深く理解しながら、「何がなんでもやり遂げる」というマインドでDXを推進しながらも、実務担当者の不安にも寄り添い、対話を繰り返すことが重要です。
当社では、技術面のサポートはもちろん、マインドセットの変革も含めたDXの推進をサポートしています。
DXとは変革です。簡単なものではないですし、全ての会社において課題は異なります。
だからこそ私たちは、お客様と一緒に「どうやったらDXを推進できるのか」を考え続けることが大切だと考えています。
※本記事の内容は2024年11月の取材をもとにしています。記事内のデータや組織名、役職などは取材時のものです。