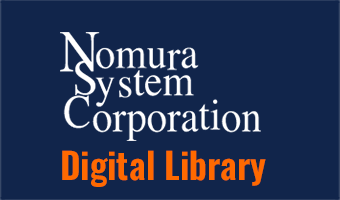人財/人材育成
2030年問題とは?日本企業への影響や対策をわかりやすく解説
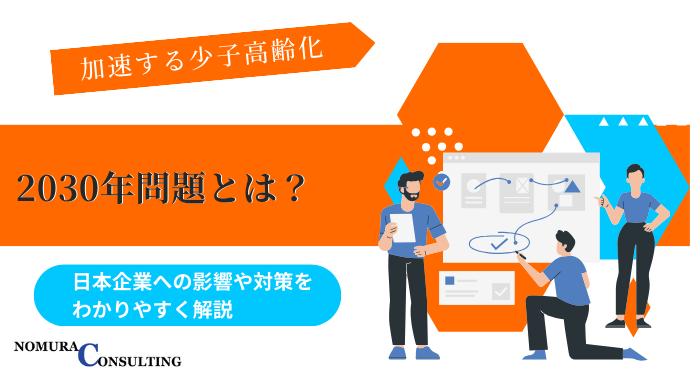
2030年問題とは、少子高齢化がもたらす社会問題のことです。
主に企業活動を支える「人材確保」などに今後影響を及ぼすため、対策を講じる必要があります。
本記事では、2030年問題の概要と企業が受ける影響、その対策として企業ができることを解説します。
2030年問題とは|少子高齢化による社会問題
2030年問題とは、日本国内において少子高齢化や人口減少が進行し、それにともなって2030年頃に起こる社会問題の総称です。
とくに、多くの日本企業における人材不足が深刻化し、2030年以降、さらに顕著な人材確保難や人件費の高騰が懸念されています。
以下では、2030年までに懸念される、高齢化と労働人口減少の現状について解説します。
2030年には高齢者人口が全人口の31.8%となる
65歳以上の高齢者人口は、2023年10月1日時点で全人口の29.1%を占めています。
さらに「国立社会保障・人口問題研究所|日本の将来推計人口(令和5年推計)」によると、2030年には、65歳以上の高齢者人口が全人口の30.8%を占める見通しが示されました。
日本では少子化により総人口の減少も顕著であり、2030年以降も高齢者人口が占める割合が増える見込みです。
2030年以降も働き手の減少傾向が継続する
2030年以降も少子高齢化・人口減少が進み、生産年齢人口(15〜64歳)は減少し続けると予測されています。
2020年の生産年齢人口は7,509万人ですが、令和5年推計値では2032年に7,000万人を切る見込みです。
この減少傾向は2040年から2050年、さらには2070年まで続くとされており、将来的な働き手の不足は避けられない状況にあります。
参考:日本の将来推計人口(令和5年推計)|国立社会保障・人口問題研究所
2030年問題が日本企業に与える影響
2030年問題により日本企業が受ける影響は、以下の通りです。
- 人材確保が難しくなる
- 人件費が上昇する
- 事業や技術の継承ができなくなる
1. 人材確保が難しくなる
2030年以降も高齢化と労働力人口減少が深刻化すると、企業は人材の確保が難しくなります。
優れた人材の獲得競争が激化し、採用難が加速するためです。
また、帝国データバンクによると、2024年の「人手不足倒産」は342件で過去最多。
2025年以降も人手不足による倒産企業は増加するとされています。
日本国内の生産年齢人口が減少している以上、業界を問わず、人材不足に直面し業績悪化につながるリスクは避けられません。
参考:倒産集計 2024年(1月~12月)|帝国データバンク
2. 人件費が上昇する
2030年問題で発生する人手不足や採用難は、人件費の高騰を引き起こします。
同業他社との人材獲得競争が激しくなる中、企業は優秀な人材を確保するために賃金や待遇の引き上げを迫られるためです。
とくに、慢性的な人手不足が予想される業界では、給与水準の上昇が避けられません。
また、人手不足の深刻化を背景に、最低賃金の継続的な引き上げや社会保険料負担の増加が進むことも、企業の人件費を押し上げる要因となるでしょう。
結果として2030年以降、中小企業を中心に経営への負担がより一層大きくなる可能性があります。
3. 事業や技術の継承ができなくなる
少子高齢化によって労働力人口が減少することにより、後継者が高齢化したり不足したりするため、事業継承ができなくなる可能性が高まります。
帝国データバンクによると、2024年の調査時点で後継者不在率の高い業界は以下の通りです。
- 建設業:59.3%
- 小売業:56.8%
- サービス業:55.5%
- 不動産業:52.9%
上記のように、技術職・専門職を必要とする建設業界や不動産業界は、高齢化と人材不足の影響をとくに受けやすく、迫る2030年問題は深刻です。
また、技術者が高齢化・リタイアすることで、技術そのものが継承できなくなる可能性も高まります。
参考:全国「後継者不在率」動向調査(2024年)|帝国データバンク
2030年問題への対策
日本企業が講じるべき2030年問題への対策としては、以下が挙げられます。
- 働き方の改革
- シニア人材・女性・外国人労働者の活用
- デジタル化・DXの推進
- リスキングの推進
1. 働き方の改革
2030年問題の最たる影響である「人材確保」への対策として、労働環境を見直す働き方改革が欠かせません。
厚生労働省も、働き方改革の実現に向けてさまざまな取り組みを行っています。以下はその一例です。
- 長時間労働の是正
- 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
- ダイバーシティの推進
- 賃金引き上げ、労働生産性向上
- ハラスメント防止対策
企業が取り組めることとしては、テレワークやフレックスタイム制の導入などが挙げられます。
また、働きがいのある職場づくりやキャリア支援の充実によって、離職率を低めることも重要です。
2. シニア人材・女性・外国人労働者の活用
シニア人材や女性、外国人労働者といった雇用者を活用するダイバーシティ推進の取り組みも、2030年問題に有効な対策となります。
ダイバーシティを推進し年齢・性別問わず受け入れることで、労働力不足の解消につながるためです。
企業は雇用する人材の幅を広げ、誰もが働きやすい環境をつくることが2030年以降に向けて求められます。
3. デジタル化・DXの推進
2030年問題に向けては、デジタル化・DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が重要となります。
DXによる自動化が進めば、省人化が可能となり、人材不足の課題を軽減できるためです。
たとえば、製造業ではスマートファクトリーの導入により生産工程の自動化が進み、小売業ではセルフレジや自動発注システムの活用が広がっています。
企業のDX成功事例については、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:DX推進の成功事例 |最新の成功事例やDX化のポイントも解説
4. リスキリングの推進
2030年問題に企業が対応するためには、「リスキリング」の推進も重要です。
リスキリングとは、異なる職務や業務に対応するために、新しいスキルや技術を学び直すことを指します。
2030年は生産年齢人口の減少が問題視されていますが、実はより顕著になるとされているのが専門技術職の人材不足です。
対して生産職や事務職は、ロボットやAIに代替・自動化されることなどにより、過剰供給となる可能性があります。
したがって2030年に向けて、企業は従業員のリスキリングを促進し、専門職への転換を支援することなどが求められるでしょう。
2025年問題・2040年問題との関係
2030年以前・以降も、2025年・2040年問題と、段階的に少子高齢化等が問題化されています。
「2025年問題」は、2025年に団塊世代(1947年から1949年に生まれた世代)が75歳以上になることで加速するとされた高齢者問題です。
また2040年は、65歳以上の人口が全人口の34.1%を占めるタイミングとされています。高齢者を支える現役世代の負担がさらに増え、社会保障制度の維持なども困難になるのが「2040年問題」です。
企業は、2030年以降も発生が予想される段階的な課題に対して、柔軟に対応していく必要があります。
2030年問題には企業として柔軟な対応が求められる
2030年問題で起こりうる人材不足・採用難に企業が備えるためには、働き方改革やデジタル化、リスキリングといった対策が求められます。
とくにDXはデジタル化により組織改革や人手不足解消につながるため、2030年に向けて推進することをおすすめします。
DXのご相談やサポートが必要な際は、ぜひ以下よりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら