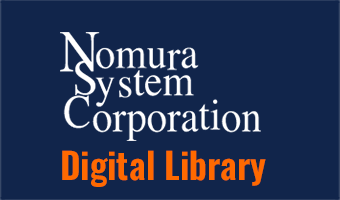コンサルタント記事
失敗しないDX導入に必要な「問題と課題の整理」|DXの現場

- 識名 祥隆
- 次世代戦略事業部 部長
「DXの現場」では、ノムラシステムコーポレーションの現役コンサルタントが、SAPの導入をはじめ、DXに20年以上携わった経験から、DXで重要となるポイントについて紹介します。
今回のテーマは「問題と課題の整理」です。DX失敗の典型例は、ツールが導入の目的となってしまい、導入前に描いていた効果が得られないことです。失敗を避けるためにも私たちは、問題と課題をツール導入前に徹底的に整理しています。
本記事では、ツール導入前の整理やその重要性、要件定義への落とし込み方についてお伝えします。
DX導入と業務改善策を提案
私は、お客様の経営課題に対する解決策として、DXの導入や業務改善策をご提案しています。
DX導入までの基本的な流れは、以下の4ステップです。
- 問題と課題の整理
- 必要機能の検討
- 条件に該当する製品を絞り込み
- システムの導入
提案時に心掛けているのは「システム導入を目的にしないこと」です。
既存のやり方や社内ルールなどをベースとして考えると、システムの導入自体が目的となってしまい、結果的に経営課題にアプローチできないことも少なくありません。
お客様と対話を重ねながら、本当の課題を洗い出し、解決策を練っていくことが、DX導入において非常に大切だと考えています。
具体的にどのように進めているのか、具体例を元にご紹介します。
【事例】従業員のスキル管理をDX化→受注可否の可視化を実現
ある建築会社では、業務の中で求められるスキルや資格の習得状況や従業員のシフトをオンライン表計算ソフトで管理していました。
業務の受注可否は、施工管理技士資格やクレーン運転免許などの専門資格を有する人材をアサインできるかどうか、が重要な判断基準となります。
しかしデータ上では1人を1シートで管理しており、シートだけで何百という膨大な数になっていたため、受注に必要なスキルを持つ人材がアサインできるかどうか、判断が難しい状況になっていました。
また、人材リソースの可視化において以下の課題がありました。
- アサイン状況と期間の把握
- 現在不足しているスキルや資格の特定
- 定年退職等による将来的に必要となるスキル・資格の予測
これらの分析や管理を既存のツールで効果的に行うことは困難であり、管理ツールとしての限界を感じていました。
そこで、
1. 業務の一部をシステムに切り替えたい
2. 組織・個人・プロジェクトに不足しているスキル・資格を把握、分析するツールが欲しい
といったご相談を受け、導入をサポートしたのが「タレントマネジメントシステム」です。
以前はオンライン表計算ソフトで個別管理されていた個人のスキルや資格情報を一元化することで、組織内のスキルギャップ、アサインメンバーの業務状況、定年退職に伴う資格保有者減少リスクなどを可視化。
業務状況が把握できるようになったことで、迅速に受注可否判断が下せるようになりました。
さらに、従業員の年次別スキル分布の可視化により、中長期的な人材育成戦略の立案もできるようになったのです。
私たちが本企業の導入にあたって重要視したことは「何が本当の問題か」を見極めることです。
ありがたいことにこの建築会社では、導入当初は限定的なDXを推進しておりましたが、現在では社内全体で複数のツールの導入が進んでいます。
継続的な利用と課題を解決してこそのDX

システムは導入がゴールではありません。導入後に継続的に活用され、当初の課題を解決して初めて「DXが成功した」といえます。
DXで失敗するケースとして最も典型的な例は、ツールの導入自体が目的となり、解決すべきビジネス課題が曖昧なまま導入を進めてしまうケースです。
たとえ最適なシステムを導入しても、従業員が利用をめんどくさがったり、操作方法がわからなかったりして、結局もとのツールを使い続けてしまっては意味がないと考えています。
ツールの導入前には、
・なぜシステムを導入したいのか
・お客様が抱えている問題と課題は何か
・何を導入することが最適か
これらの問いを、お客様に繰り返しヒアリングしています。
「問題と課題」の整理
DX導入前に重要となるのが「問題と課題」です。
問題: 理想に辿り着けない原因
問題とは、理想とする姿までに辿り着けていない原因のことです。DXを検討している企業であれば、目指している未来と現状の違いを作り出している理由が問題にあたります。
課題:理想の姿になるための施策
課題とは、現状から理想の姿になるための施策のことです。企業が抱えている問題の解決策として、浮かび上がるのが課題といえます。
私がお客様よりお話を伺う際に、最も意識しているのがこの「問題と課題」です。
問題と課題を的確に切り分け、組織の現状を分析できなければ、不要なシステム導入やDX化の失敗にもつながりかねません。
必要機能の検討
問題と課題が整理できたら、必要機能の検討フェーズに移行します。この段階では、解決策としてのシステムに求められる具体的な機能要件を要件定義書として文章化します。
要件定義を実施する際のコツは、以下の3つです。
- 課題を箇条書きする
- 課題は徹底的に細分化する
- 課題と施策は1対1対応させる
例えば、「英語力の管理をしたい(機能要件)」という目的であれば、
英語力の判定基準を、TOEFL、TOEIC、EFSET、IELTS、ケンブリッジ、英検といった6項目を定めた上で、
初級の基準は以下とする
- 英検の場合⚪︎級
- TOEFLの場合⚪︎点…
と、上記のようにどんどん書き出しながら進めます。
先述した建築会社の時は、機能要件はヒアリングシートで50 〜 60行ほどになっていました。
このように、要件定義を事前に作成して初めて、目的を解決するためのツールが導入可能となります。
その後、要件定義に基づいたツールの選定を行い、具体的な機能要件と適合性を精査。最終的なツールを決定したのち、実装フェーズへと移行します。
このような流れで、お客様の目指す理想と解決しなければならない課題を明確にし、お客様の目的に合わせた施策や業務改善手法を提示するのが、私たちの仕事です。
「お客様目線」が私のこだわり
私がお客様とお話する上でこだわっていることが2点あります。
- お客様にとって最適な提案をすること
- お客様とワンチームになること
1. お客様にとって最適な提案をすること
一つ目のこだわりは、「お客様にとって最適な提案をすること」です。
組織の内部にいると、先入観や思い込みから、自社の問題や課題に対する客観的な判断は困難です。だからこそ、外部のコンサルティングが客観性の担保という重要な役割を担っています。
私たちはDX導入プロジェクトの開始に先立ち、お客様と徹底的な対話を通して、客観的に問題と課題の把握に努めています。
効果的な提案を実施するためには、お客様との連携が必要不可欠です。特に、ヒアリング段階での密なコミュニケーションは、本質的な経営課題の解決につながるDX導入の基盤となります。
私の最大のモチベーションは、お客様の期待を超えた提案ができた瞬間です。想定以上の提案を受けて喜んでいただいた際の「お客様の笑顔」が私のやりがいですね。
2. お客様とワンチームになること
二つ目のこだわりは、「お客様とワンチームになること」です。
ワンチームとは、お客様と私たちが同じ目標を共有し、プロジェクトの成功を目指すことです。
システム導入の成功は、お客様といかに「ワンチーム」になれるかどうか、がカギだと考えています。
DXプロジェクトにおいては、経営戦略の決定から現場の実践まで、お客様が主体となった推進が必要不可欠です。
一方私たちは、立場としては「黒衣(クロゴ)」ですが、お客様と同じ目線で課題と向き合い、戦略の立案から実行までを共に推進するパートナーとして、お客様にご納得いただける成果を出してもらいたいと考えています。
まとめ:「問題と課題」の整理がDXの成否を分ける
DXプロジェクトの成否を分けるのは、「問題と課題の的確な整理」にあります。
私たちが考えるDXの成功とは、単なるシステムの導入ではありません。現場の方が継続的にシステムを活用し、当初想定していた課題を解決して初めて、お客様に満足いただける価値を提供できるのだと考えています。
システムの導入や、導入したけど現場に浸透しないことにお悩みの方、これから導入を検討を始められる方に、ぜひ私たちの知見をお役立ていただけたらと思います。
※本記事の内容は2024年11月の取材をもとにしています。記事内のデータや組織名、役職などは取材時のものです。